仮想通貨の価格分析といえば、テクニカル分析、オンチェーン分析、センチメント分析、マクロ経済分析がよく語られる。
しかし、本質的にもっと重要な要因がある。
それが市場構造と資金の流れ方だ。
どのような配管が整備され、どこに蛇口が増え、どの器に水がたまりやすいか。
これを理解すれば、次に資金が流れ込む先を先回りできる。
この記事では、クリプト市場の構造がどう変化してきたのか、いま何が起きているのか、そして次のサイクルに向けて何が変わり得るのかを体系的に整理する。
市場構造の進化史――「買えるようになる」ことがすべて
2009〜2010年:原始的な取引
ビットコイン誕生直後は、掲示板やフォーラムでのP2P取引が中心だった。
2010年3月には初の取引所BitcoinMarket.comが登場し、同年7月にはMt.Goxが開設。
ここで初めて「マーケット」という形ができた。
2014年:Tetherによる銀行問題の突破口
USDT(当初はRealcoin)が誕生。
取引所がドル建て取引ペアを提供しやすくなり、銀行依存を減らす大きな転換点になった。
取引所は法定通貨を直接扱わなくても、USDTを介して市場を回せるようになったのだ。
2015〜2017年:伝統金融の入り口が開く
2015年、スウェーデンでCoinShares(旧XBT Provider)が世界初のビットコインETPを上場。
2017年12月にはCMEがビットコイン先物を上場。
これにより「クリプトは正規の資産クラス」という認識が広がった。
2017年:市場の本格化
この頃、CoinbaseやGeminiのような規制準拠型取引所が銀行との関係を改善し、入出金がしやすくなった。
市場規模は2017年末に約7,500〜8,000億ドルに到達。
だがまだ「買える場所が少ない」時代だった。
2021年:資金流入の爆発
市場規模は一気に約3兆ドルまで拡大。
ETFや取引所整備により資金流入の配管が太くなり、ユーザーも急増した。
初期に比べ「買える」こと自体が圧倒的に容易になった。
2024〜2025年:UX革命
米国でスポット型のBTC・ETH ETFが承認され、FidelityやBlackRockといった伝統資産運用会社も自社ソリューションを提供。
さらにCoinbaseのL2「Base」やSolanaの「Phantomウォレット」が普及し、銀行口座やカードからワンタップでオンチェーンに資金を流せる環境が整った。
つまり、資金の入口は過去最大に整備されたのだ。
今サイクルの上値余地を構造から逆算する
株式保有率は先進国で約6割だが、暗号資産はまだ2割程度。
入り口の整備とUXの進化により、投資家数が株式並みに近づく可能性は高い。
もし投資家数が倍増し、1人当たりの流入額が維持されれば、時価総額は6〜9兆ドル規模に到達するシナリオも現実味を帯びる。
ビットコイン優位は続くが、実際に大きな伸びを見せるのはUXが優れ、流動性が高く、取引しやすいアルト群だ。
市場ドミナンスの低下は、資金が次のフロンティアを探している証拠でもある。
誤解を正す:よくある3つの神話
神話1:アルトが増えすぎて流動性が希釈されている
実際には人間が取引している“質の高い”アルトは限定的。
CoinGeckoが追跡する銘柄数は2021年の約1万から現在は約1.9万程度。
倍増はしているが、投資家数と資金流入の増加で十分相殺され得る。
神話2:ETFがあるからBTC/ETHからアルトに資金は回らない
大口投資家はBTC/ETHを売らずに担保にしてUSDCなどを借り、アルトを買う。
ETF流入→BTC/ETH価格上昇→担保価値増→借入余力増→アルトへの流入増という二次効果が働く。
神話3:給付金がなければ相場は盛り上がらない
調査では、コロナ給付金の多くは消費・貯蓄・負債返済に回った。
株式や一部クリプトにも流入したが、相場を押し上げた最大の要因は資金ではなく時間=人々の注意だった。
2020〜21年は世界がロックダウンされ、学習と投資に集中できたのだ。
最大の制約は「注意の寿命」
2021年は長期的な回転相場が可能だったが、2024年以降のラリーは2〜3カ月で終わることが多い。
理由はシンプルで、人々の注意が分散し、持続しないからだ。
資金はあるが、熱狂を維持できない。
これが今サイクルの特徴だ。
したがって、短期で注意を集められる銘柄、そして「すぐに買える」銘柄が勝つ。
長期的な物語や技術力は重要だが、それだけでは資金流入は持続しない。
次サイクルに向けた変化:伝統金融の本格参入
法規制の整備
米国では2025年に「Genius Act(ステーブルコイン規制法)」が成立、施行は2027年予定。
「Clarity Act」も議論されており、成立すれば暗号資産全般の法的枠組みが整う。
銀行ステーブルコインの可能性
JPモルガンやバンク・オブ・アメリカのようなメガバンクが自社ステーブルを発行すれば、既存のUSDTやUSDCより発行・償還のUXが優れる可能性が高い。
混乱期には「銀行ブランド」へ資金が逃避するリスクもある。
トークン化証券(RWA)の拡大
NASDAQはトークン化証券の提供を模索し、Geminiに出資している。
次のベア市場では、伝統金融が暗号資産企業を買収・吸収し、次サイクルのインフラを握るシナリオが現実味を帯びる。
結論として、次のサイクルは「クリプト市場」というより「デジタル資産市場」へと変容する可能性が高い。
淘汰は厳しくなるが、新しい投資対象(RWAや新型トークン)が次々と生まれるだろう。
投資家が押さえるべき戦略ポイント
- コア資産はBTC/ETH
ETFやDeFiの担保として機能し続ける。
売らずに保有し、借入やステーキングで副次的リターンを検討。 - アルトは「アクセス容易性」で選ぶ
グローバル取引所に上場済み、またはUXが優れたウォレットで簡単に買える銘柄。
Solana、Baseエコシステムはその典型。 - 注意の寿命を前提に設計
短期(2〜3カ月)での注目テーマに合わせ、目標と撤退基準を明確化する。 - 流動性の太さを最優先
板が厚く、ステーブルとのペアが豊富な銘柄を優先。 - 規制動向を常に追う
法制度の施行が近づけば、勝者と敗者が大きく分かれる。
結論――物語ではなく配管を見よ
暗号資産の未来を決めるのはストーリーではない。
資金の入口と出口がどこにあり、どれだけ摩擦が少ないかだ。
Mt.Goxから始まった細いパイプは、いまやETF、銀行、ウォレット、ブリッジと無数の蛇口につながっている。
そして次サイクルでは、伝統金融がその配管をさらに拡張し、主導権を握るかもしれない。
淘汰は避けられないが、「買いやすい資産」こそが勝ち残り、最も大きな値動きを生む。
クリプトの未来を読むには、チャートよりもまず市場構造という配管図を描く。
そこに、次のラリーの答えが隠されている。

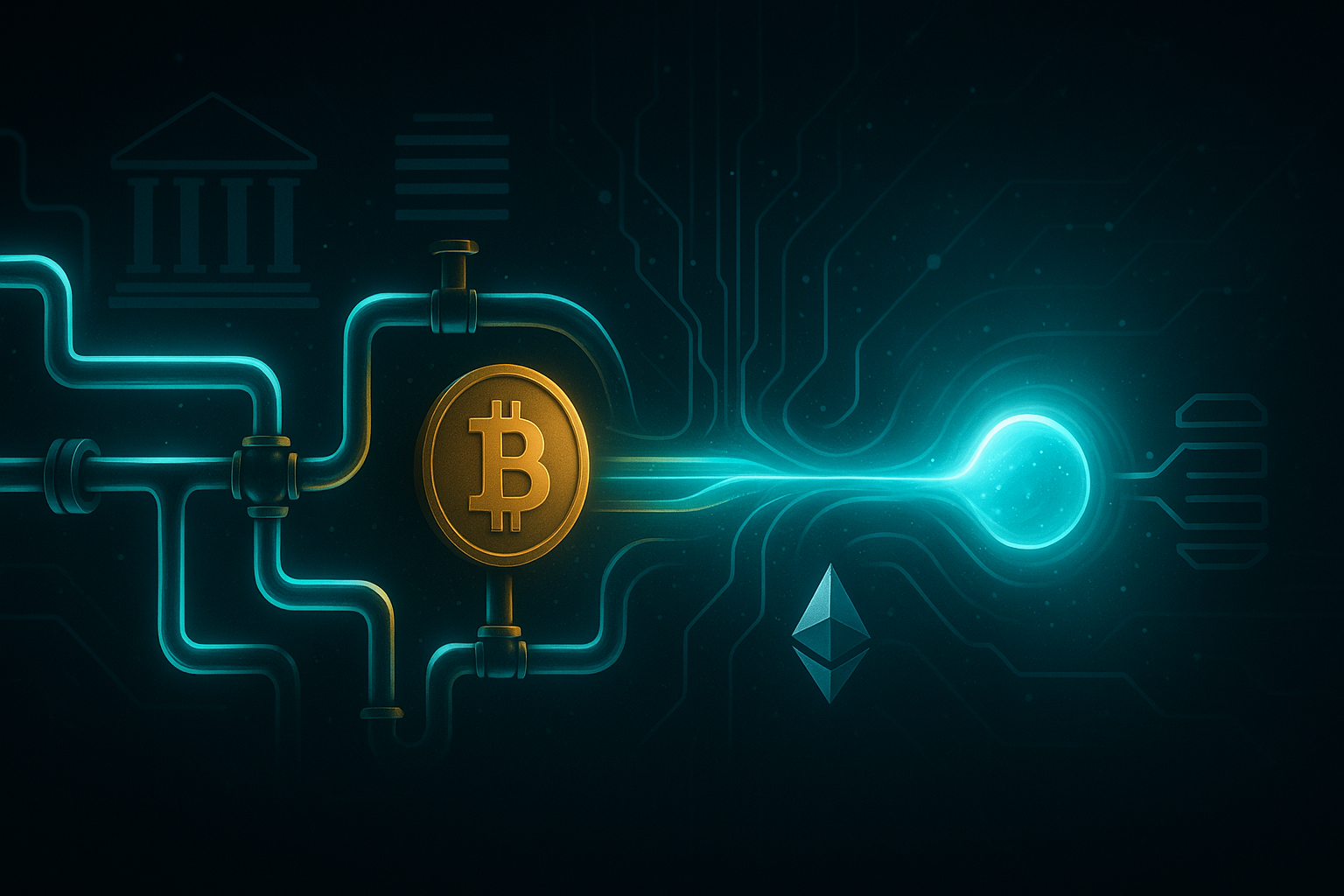
コメント
コメント一覧 (1件)
фильмы онлайн сериалы про вампиров и оборотней