デリーで行われた約7時間に及ぶ米印の通商協議は、公式な「第6ラウンド」ではなく、その準備段階の話し合いだった。
米国からはブレンダン・リンチ首席交渉官率いるチーム、インドからは商工省のラジェシュ・アグラワル特別官を中心とする当局者が出席し、双方は「前向きだった」と口をそろえた。
数カ月間の混迷と緊張を経て再び交渉が軌道に乗り始めたが、その裏には高関税、ロシア産原油、農業市場アクセスといった複雑な問題が横たわっている。
交渉が一時停止した理由
- 関税の衝撃
米国はインド産品に最大50%の追加関税を課し、さらにロシア産原油の輸入を理由に25%のペナルティを上乗せした。
これにより予定されていた8月下旬の第6ラウンドは中止に追い込まれ、信頼関係は大きく揺らいだ。 - 農業・畜産の赤線
米国はインドの農業、酪農、水産、さらには遺伝子組換え作物に対して市場を開放するよう求めている。
しかしインドは「農民や漁業者、畜産業者を犠牲にする妥協はあり得ない」と断固拒否。
この立場は一貫している。 - ロシア産原油をめぐる圧力
米国はインドがロシアからエネルギーを輸入し続けることを問題視。
しかし国際法的には違反ではなく、インドは「国内のエネルギー安全保障のため当然の選択」と冷静に応じた。
インドの対応:粘り強さと戦略的忍耐
元通商長官アジャイ・ドゥア氏は、「米国の一方的な関税措置や非難に対しても、インドは感情的に反応せず外交的に処理した」と強調する。
実際、インド政府は強硬な発言を控え、外務省の報道官レベルで淡々と対応。
ホワイトハウスやトランプ大統領から前向きな発言が出れば、モディ首相や閣僚が即座に応じるという「静と動」のメリハリで交渉を維持してきた。
米国の本音と交渉スタイル
米国側は「最大圧力戦略」を好む。
農業市場の全面開放やゼロ関税を求めつつ、自国の産業は守る姿勢だ。
アナリストのアジャイ・バッガ氏は「今回の関税はインドを“見せしめ”にした側面がある。トルコや中国の方がロシアとの貿易規模は大きいが、狙い撃ちされたのはインドだった」と指摘する。
つまり、インドに対して「国際市場での挑戦は簡単ではない」というメッセージを送った形だ。
軍事・外交チャネルは継続
一方で、貿易以外の対話は止まっていない。
9月初旬にはアラスカで米印合同軍事演習「ユッド・アビヤス」が予定通り実施され、2+2閣僚対話も継続。
防衛装備や研究協力の話も進行中で、関係全体が断絶しているわけではない。
国際関係学者スワラン・シン教授も「関税や発言のトーンに左右されすぎず、大局的に関係は維持されている」と評価する。
今後のシナリオ
- ミニ・ディール実現
11月までに農業以外の分野で「早期収穫(アーリーハーベスト)」と呼ばれる小規模合意が成立する可能性。
関税の段階的引き下げ、検疫や通関手続きの改善、デジタル分野の協力が対象になりやすい。 - 停滞の継続
高関税は維持されたまま、品目ごとに例外措置を設ける形。
交渉は続くが、大筋合意は遠い。 - 再燃リスク
新たな地政学的イベントや米国の強硬発言で関税が再度エスカレートする可能性も残る。
■ 投資家・企業へのインプリケーション
- 輸出業者(宝飾・繊維・水産)
8月の対米輸出は前月比で約12億ドル減少。
短期的にはホリデー商戦への打撃が懸念されるが、第三国経由や代替市場の開拓で一定の緩和が可能。 - エネルギー・運輸
調達多角化と為替ヘッジが必須。
米国からの原油購入が条件に入る可能性もあり、価格競争力とのバランスが焦点。 - 防衛・航空
ボーイングやエアバスからの調達案件は交渉カードに使われやすい。
ただし「性能・コスト・運用」の3条件に合致するかどうかが最終判断。
筆者の考察:段階的合意こそ現実解
全面的なBTA(包括的貿易協定)は短期的には非現実的だ。
現実的シナリオは
①関税ペナルティの縮小 → ②実務改善(通関・検疫) → ③農業分野の限定的テスト → ④デジタル・投資協力の拡大
という順序で信頼を積み上げていくことだ。
市場は「関税ヘッドライン」に過剰反応しがちだが、本当に注目すべきは通関日数やSPS承認率といったKPIだ。
これが改善すれば、企業収益と投資機会は確実に広がる。
インドは「粘り強く譲らないが、関係を壊さない」という姿勢で一貫している。
この戦略が功を奏すれば、米国との交渉は断絶ではなく「難航しつつも前進」という形で続くだろう。
そしてその先に見えるのは、全面BTAではなく積み上げ型のミニ・ディール連鎖。
それこそが、両国にとって現実的かつ持続可能な道筋だ。

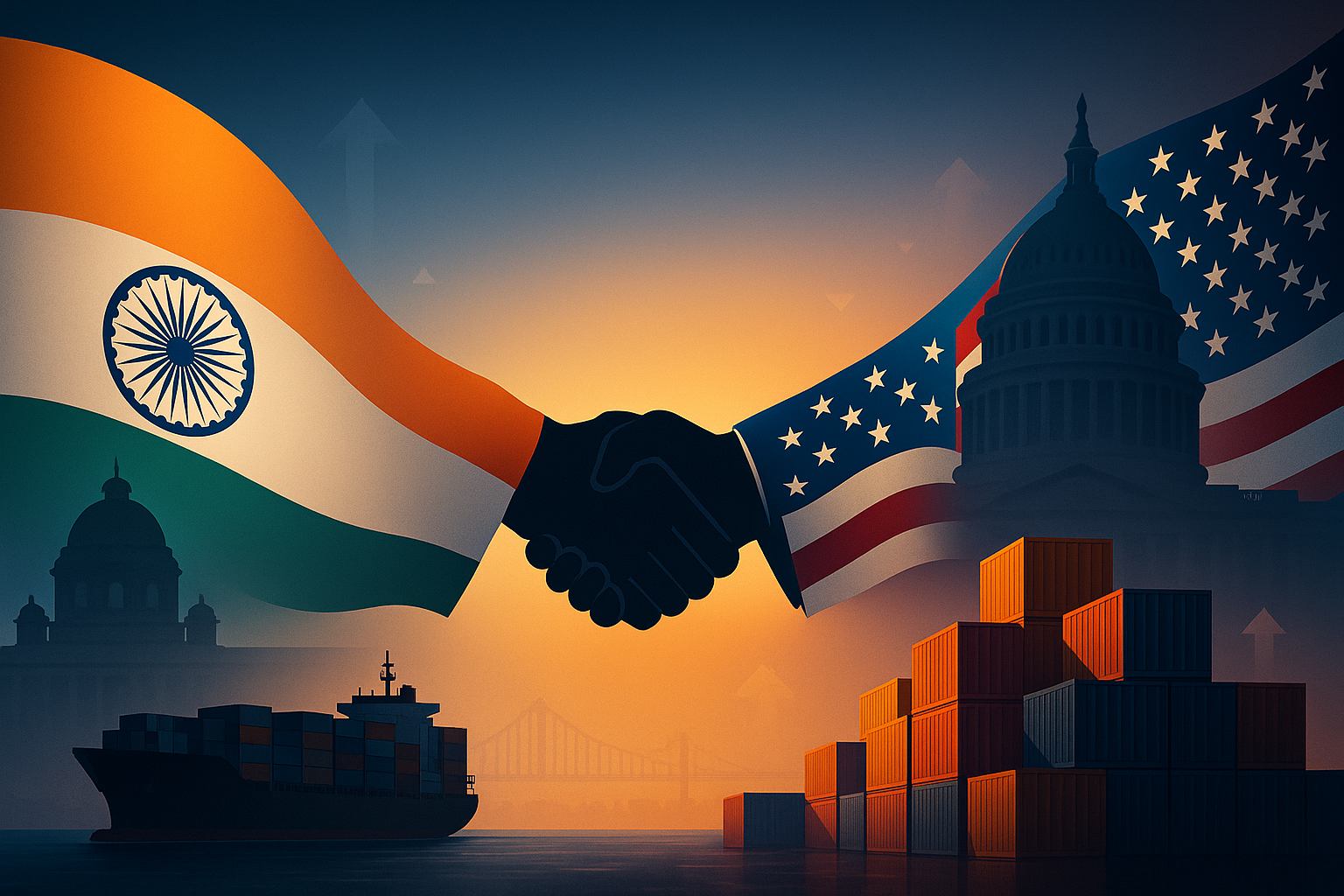
コメント