2024年にスポーツ特化ファンドを立ち上げた著名投資家マーク氏へのインタビューは、今この領域が本格的な投資アセットへと昇格しつつある現実を生々しく示している。
彼の主張は端的だ。
スポーツはまだ「第1回表」始まりの始まりで、機関マネーの競合が少ない。
可視化すると、機会は総額1兆ドル規模に対し、実際にぶつかっている資金は約100億ドル。
需給の非対称が生む歪みこそが、彼の勝ち筋である。
本稿では、このインタビューで語られた要点を整理しつつ、収益モデル・バリュエーション・規制の壁・運用実務を投資家目線でかみ砕く。
女子サッカーやWNBA、PBR(Professional Bull Riders)、マイナーリーグ野球、TGL(テクノロジー×ゴルフの新機軸)、そして将来のNBAヨーロッパまで、“エマージングリーグの複利”をどのように捉え、ポートフォリオに実装すべきかを解説する。
💰ファンドの現況と資金配分
マーク氏のファンドは10億ドル超を調達、約半分を既に投下。
残りのドライパウダーで狙うのは、女子サッカー、WNBA、マイナーリーグ野球、PBRなどのエマージング領域が中心だ。一方で、NBAやNFLといったメジャーリーグへの参画意欲も維持している。
つまり、戦略は二段構え。
1つは安定成長の“コア”としてのメジャー。
もう1つは“オポチュニスティック”に複数倍を狙うサテライトとしての新興リーグ群だ。
📈期待リターンの非対称──メジャーは年率10〜15%、新興は5〜50倍も
メジャーリーグ投資の想定は年率10%前後。
新メディア契約の更新が重なる局面では15%程度の上振れも見込む。
一方、エマージングは5倍、10倍、20倍、50倍の可能性に言及。
もちろん成功確率はメジャーに劣るが、分散ポートフォリオで“バスケット”として捉えれば、ファットテールが効きやすいのがこの領域の魅力だ。
投資家に重要なのは、確率×規模×時間の三点掛け。
メジャーは高確率で適正リターン、新興は低確率でも的中時の損益寄与が巨大。
この非対称性を資本配分で最適化する設計思想が必要になる。
📺レベニューの三本柱と“裁定”──チケット、スポンサー、メディア権
スポーツの収益源はチケット、スポンサー、メディア権の三本柱。
マーク氏は三つとも過小評価されていると見る。
特にメディア権は裁定の宝庫だ。
例として挙げられたPBRは、平均視聴者数がMLBの1試合平均に匹敵する局面もあるのに、メディアバリューは明らかにディスカウントされている。
ここに「視聴実績に対し、放映権価格が追いついていない」ギャップがある。
契約更新の度に段階的なリプライシングが進み、スポンサー単価と同時進行で圧縮バリュエーションが解消される。
投資家にとっては“時間が味方する裁定取引”に近い。
🐂PBR(プロ・ブルライディング)──数字が背中を押す「ニッチの王者」
PBRはイベント当たりの満足度が極めて高く、来場者の95%が“好き”と回答する水準。
約3分ごとに熱狂の見せ場が訪れる競技設計は、ショートアテンション時代のテレビ・配信フォーマットと相性が良い。
視聴の裾野が広がるほど、スポンサーのCPS(Cost per Smile)=笑顔のコストは低下し、売り手市場化が進む。
放映権の再評価→スポンサー単価の上昇→チケット価格の順次見直しと、三本柱が“追い風の循環”を形成する。
🏀WNBAと女子サッカー──“構造的アンダーバリュー”の筆頭
マーク氏はWNBAと女子サッカーの成長を強調。
女子は国際大会→SNS波及→スターの可視化のパスが年々加速し、スポンサーが“文脈の合致”で入札しやすい。
加えて女子スポーツは新規視聴者(新規課金者)を獲得しやすく、ARPUの伸びしろが大きい。
一方で、チーム移転や市場再配置にはリーグ承認という規制の壁がある。
コネチカット・サンのハートフォード移転の構想は、NBA側の管轄・市場調整の論理が働くためハードルが高い。
これは規制・統治(ガバナンス)リスクの好例で、評価モデルに“承認確率と時間の値引き”を組み込むべき点だ。
⚾マイナーリーグ野球──“運営の科学化”で利益率を押し上げる
マイナーはテレビマネーではなく、オペレーション改善が肝。
マーク氏の仮説はシンプルだ。
複数球団を束ねることで
・デジタル集客のスケール化(共通CMS、広告運用、CRM)
・スポンサー営業の広域化(パッケージ販売)
・イベント企画の横展開(成功フォーマットのテンプレ化)
が効き、固定費逓減と売上の天井引き上げが同時に起きる。
「家族で来やすい価格×体験価値の最大化」が勝ち筋だ。
🎮TGL(テクノロジー×ゴルフ)──21〜35歳の“2時間インタラクティブ”
TGLは選手の会話が聞ける近接体験と2時間完結のショートフォーマットで、Z世代〜ミレニアルの視聴設計に最適化。
長時間の18ホール視聴に慣れていない層に、新しい接点を提供する。
ゴルフの裾野拡大×配信の相性を先取りする形で、スポンサー単価→配信権の評価を押し上げるトリガーになりうる。
🌍NBAヨーロッパ構想──“ブランド統治”が生むプレミアム
バスケットボールは欧州で裾野が広く、NBAのブランド統治で“運営品質”が一段引き上げられる。
想定は10チーム規模。都市選定(ロンドン、パリ、ベルリン、マドリード等)は航空ネットワーク・富裕度・企業スポンサー母集団で評価すべきだ。
チーム単位の投資となる見込みで、為替と渡航コストもP&Lに効く。
ここは「グローバルIP×ローカル興行」の掛け算。
IPの“外部監査”としてのNBAロゴが、スポンサーの安心と価格決定力をもたらす。
🧭規制・ガバナンス・勝率──リスクはどこに潜むか
移転承認リスク
市場の再配置はリーグの公益判断が優先。
承認確率×所要時間をディスカウント。
勝利のプレミアム
勝つほど評価倍率とスポンサー単価が上がる。
ただし選手獲得・維持コストも増すため、「勝利による限界収益>限界費用」の設計が要諦。
コンプライアンス
サラリーキャップや契約規範は逸脱コストが極大。
「勝つが、規則は破らない」が前提。
集中リスク
資産の過度な単一チーム依存は避け、リーグ横断×地域分散で政治・規制の相関を下げる。
🏫大学スポーツの“収益シェア商品化”──NIL時代の資金調達
トップ校は選手への支払い圧力が増大。
寄付だけで賄えない現実に対し、将来収益の一定比率を投資家に販売するスキームが検討されている。
例えば売上1億なら10%=1000万の権利を、倍率10〜15倍などで売却するイメージだ。
これはエクイティでもデットでもない“リベニューシェア型”で、初期資金で戦力整備→勝率上昇→売上増→投資回収の循環を狙う。
ただし前例が少なく“最初の一校”が出づらい。
投資家は契約の執行可能性・開示慣行・会計処理を精査する必要がある。
🪙メディア権アップサイドの数え方
ひとつの目安は
- 視聴実績と同ジャンルの比較単価差
- 契約改定までの残存期間
- 配信プラットフォームの入札競争
- スポンサーのCPM改定余地
この4点の組み合わせで、「複利の発火点」がいつ来るかを逆算する。
入札者の増加は単価だけでなく契約条項の投資家好転(期間、オプション、国際配信)が連鎖し、バリュエーションの再定義を迫る。
🧪実務ガイド──個人投資家・ファミリーオフィスの入り口
スポーツ投資を実際に始めるには、ETF・個別株・クラブ債など多様な入り口があります。
資産規模やリスク許容度に応じて「どこから触れるべきか」を整理した詳細な解説は、こちらの記事でまとめています。
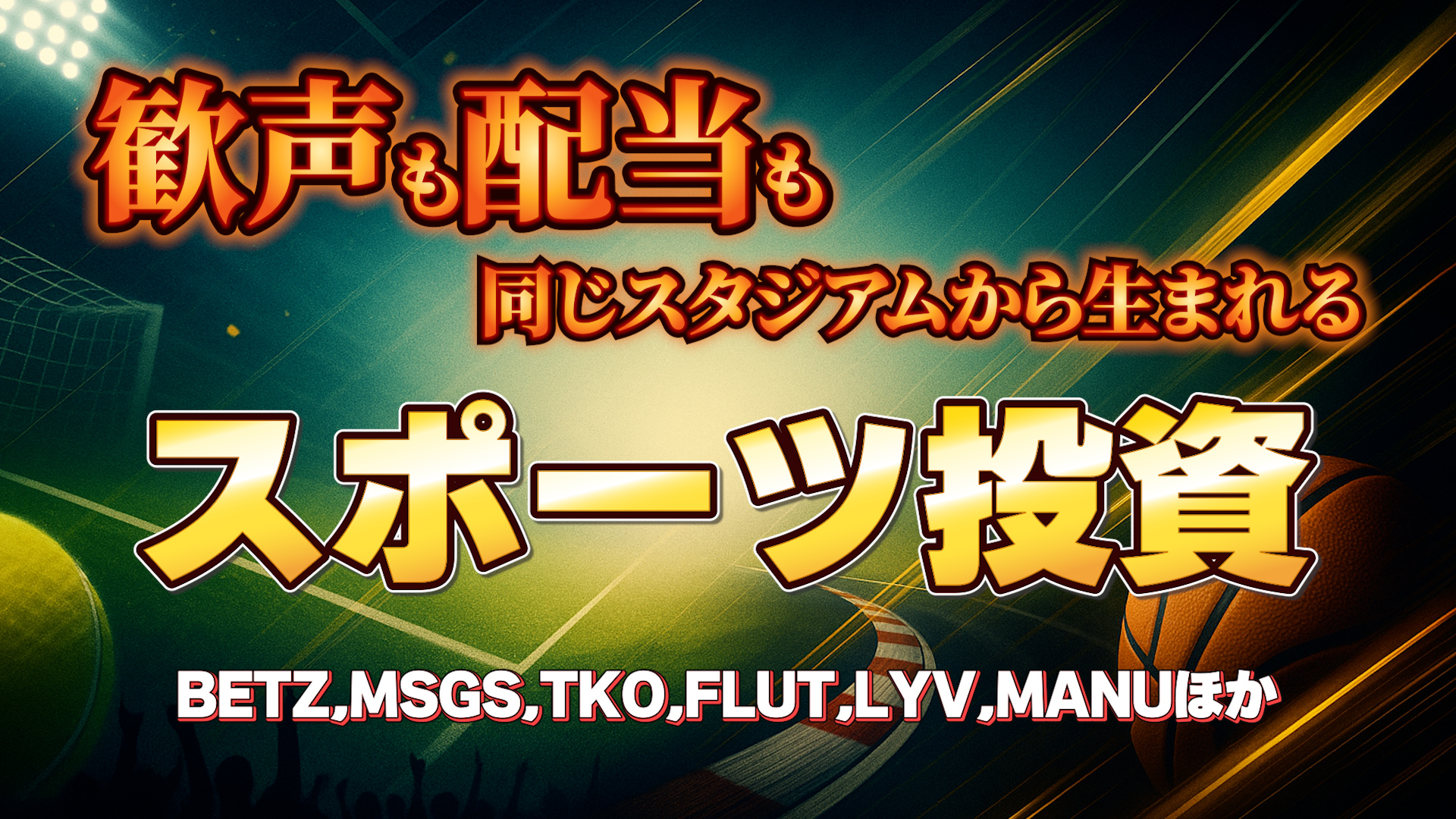
🤝「勝つこと」の経済学──感情曲線とキャッシュフロー
ファン心理は価格弾力性に直結する。
勝利はチケット・スポンサー・メディアのすべてに同時多発的な上方圧力を与えるが、一過性で終わらせない“制度化”が鍵。
例えば
・勝利翌日の継続購買導線(メルマガ、アプリ通知、限定EC)
・選手の語りを可視化(ポッドキャスト、舞台裏映像)
・地元企業の“勝利パッケージ”(勝ったら追加掲出)
など
勝利→売上の伝達経路を設計図として固定化することで、収益のボラティリティを“良い方向”に偏らせる。
🧩筆者の視点──“競技×メディア×街づくり”の統合事業
このインタビューの示唆は、スポーツが“放映権だけのビジネス”から、“統合型都市コンテンツ”へと進化していることだ。
会場の回遊性、地元企業との共創、デジタル双方向性、越境EC、観光と宿泊まで視野に入れると、NPVの源泉は会場外にこそ広がる。
エマージング領域では、競技そのものの面白さ×メディア露出の伸びしろ×ローカル経済の底上げが同時に走る。
ここで最も希少なのは「運営OS」=再現可能な運営ノウハウだ。
PBRのテンポ設計、TGLのインタラクション設計、マイナーのスケール運営は、どれもOS化すれば他競技へ横展開可能な“事業資産”になる。
結論として、コアにメジャーの安定複利を据え、サテライトでエマージングのファットテールを狙う。
その際、メディア権の裁定解消タイミングと運営OSの外販可能性を重ね合わせると、ダウンサイドは運営改善、アップサイドは権利再評価の二段構えが成立する。
スポーツ投資の本当のキモは、チームの勝敗ではなく“勝利を収益に変換する回路設計”にある。
いまはまだ第1回表。
審判の笛は鳴ったばかりだ。


コメント
コメント一覧 (1件)
Guys, Homebet88 is okay from what I saw. Nothing too crazy, but it’s worth a look! homebet88