📚 出典・論文情報
論文タイトル:Wealth Creation in the U.S. Public Stock Markets 1926–2019
著者:Hendrik Bessembinder(アリゾナ州立大学)
(米国公開株式市場における富の創出 1926年から2019年まで)
なぜ“9割の銘柄”は市場平均を下回るのか?
「どの銘柄を選べば増えるの?」
この問いに正面から答えるほど、個別株は難しいのが現実です。
なぜなら、上場企業の過半が長期では“負け”で、市場全体の勝ちの大半は“ごく一部の超勝者”に集中しているから。
だからこそ、“当てにいく”より“取りこぼさない”設計に発想を切り替える必要があります。
ssrn_id3728842_code667
市場全体は勝つのに、個人投資家が負ける理由
本研究は1926〜2019年に上場した米国株26,168社を1社ずつ“現金まで含めた最終的な富の増減”で測り直しています(SWC=Shareholder Wealth Creation)。
指標は「その会社に投資せずTビル(一ヶ月物)に置いていたら得られた金利」との差額です。
配当・自社株買い・増資まで反映する“実額の成果”と考えてください。
ssrn_id3728842_code667 ssrn_id3728842_code667
結論はシンプルで強烈。
- 市場全体は+47.4兆ドルの富を創出(Tビル超え)。
ssrn_id3728842_code667 - 個別株の57.8%は“負け”(Tビル未満)。
勝ちの大半は少数銘柄に集中。
ssrn_id3728842_code667
さらに直近3年間(2017–2019)は偏りが際立ち、全上場4,896社のうち0.16%(8社)だけで“総プラスの富”の25%を生みました。
0.98%(48社)で半分です。
ssrn_id3728842_code667
勝者総取り時代の最適解:コア&サテライト戦略
“取りこぼさない”コア+“狙って学ぶ”サテライト。
この二階建てでほぼ全て解けます。
コア=広く・薄く・自動で持つ(市場インデックス)。
超勝者が誰かは事前に特定不能。だから市場ごと抱える。
実際、市場全体は+47.4兆ドルの“果実”を出してきた。
ssrn_id3728842_code667
サテライト=小さく仮説に賭ける(産業・テーマ・一部個別)。
例えばヘルスケア/テレコムは“所属企業数の比に対して”より多くの富を生みやすかった(相対効率)。
テレコム1.77/ヘルスケア1.49/テクノロジー1.34。
テックは“額”では最大だが、群としては波が大きい。
ssrn_id3728842_code667
重要な直感:リターン分布は右に長い“歪み(ポジティブ・スキュー)”。
平均を押し上げるのはごく一部。
無作為な集中投資は市場平均を下回る確率が高い。
ゆえに低コスト分散が合理的、という理屈です。
ssrn_id3728842_code667
きょうからできる5ステップ
以下は初心者向けの実装レシピ。
1. 配分を決める(紙に書く)
- コア80%:世界/米国の広い指数を毎月自動積立
- サテライト20%:
- A:10% … テレコム・ヘルスケアに寄せたETFや厳選ファンド
- B:10% … テックの“勝者候補”(テーマETF中心。個別はさらに少額)
2. 自動化する
- 毎月同額の積立で時間分散。
- 売買判断を“考える前に自動で終える”設計に。
3. 年1回“比率だけ”直す
- 値上がった部分を少し売り、減った部分を買い足して最初の比率へ戻す(感情を封じる儀式)。
4. 学びの余白を残す
- サテライトは“授業料”の意識で小さく。
- 成果や失敗をメモ→翌年の配分微調整に活かす。
5. 絶対にやらないこと
- ニュースで配分をコロコロ変える
- 短期の値動きで積立を止める
- サテライトをコアより大きくする
この設計が向く人・向かない人
この設計が合う人
- 仕事や学業が忙しく、“放置で増える”土台を作りたい
- 超勝者を外したくないが、個別当てモノは避けたい
- ルールを決めたら機械的に続けられる
合いにくい人
- 一発逆転を好む
- 日々の値動きに耐えられない(積立を途中で止めがち)
直近の偏りは特に強く、2016→2019の市場全体の増加分の22.1%を、Apple・Microsoft・Amazon・Alphabet・Facebookの5社だけで説明。
「少数が全体を動かす」現象はむしろ強まっています。
ssrn_id3728842_code667 ssrn_id3728842_code667
“取りこぼさない投資”が未来の富を運ぶ
これだけでOK。
- きょうコア80%/サテライト20%を紙に書く
- ブローカー/証券で自動積立を設定
- サテライトはテレコム・ヘルスケア比重のETFに10%、テック系テーマに10%
- 年1回だけ作業(比率を戻す)
- 最低3年は手を加えない
なぜ“コア&サテライト”が機能するのか
① 「富の測り方」が現実的
この研究のSWCは現金の出入りをすべて拾って、最後に“もしTビルだったら”との差額で確定します。
配当・自社株買い・増資が結果に反映され、“最終的にいくら富が増えたか”をドルで見るため、投資家の実感に近いのが強みです。
ssrn_id3728842_code667 ssrn_id3728842_code667
② 「多数派は平均未満」=分布の歪み
長期の株式リターンは右に長い尾(ポジティブ・スキュー)。
平均を押し上げる少数の超勝者に出会えないと、無作為に選んだ集中ポートフォリオは市場平均を外しやすい。
よって“低コストで市場全体を持つ”戦略が、初心者ほど再現性が高い。
ssrn_id3728842_code667
③ 「勝者集中」は年々強まっている
0.16%→全体の25%(2017–2019)という極端な集中は、“勝者総取り”構造の表れ。
インターネット経済がそれを後押ししている可能性も指摘されます。
だからこそ“広く保有して取りこぼさない”が合理的です。
ssrn_id3728842_code667 ssrn_id3728842_code667
④ 産業ごとの“効率”でサテライトを賢く
テレコム1.77/ヘルスケア1.49/テクノロジー1.34。
“所属企業数に比べてどれだけ富を生みやすかったか”を見ると、意外に地味な領域が強い。
これをサテライト配分に生かすのがコツ。
ssrn_id3728842_code667
⑤ 時期によって“地合い”は大きく異なる
2017–2019は過去最大の+10.87兆ドル(三年合計のネット富創出)。
一方で1930–32、1999–2001、2008–2010などはネットでマイナスの時期も。
積立+長期+年1回の調整だからこそ波をならせる。
ssrn_id3728842_code667 ssrn_id3728842_code667
まとめ(1段で言い切る)
- 市場総体は大きく富むが、個別の多数は沈む。
- だから、“コアで丸ごと・サテライトで小さく”。
- これが、超勝者の果実を自然に受け取る最短ルート。
出典
出典:Hendrik Bessembinder, Wealth Creation in the U.S. Public Stock Markets 1926 to 2019, 2020(最新稿)。主要数値:市場+47.4兆$、負け銘柄57.8%、0.16%の企業が25%の富(2017–2019)、産業の相対効率(テレコム1.77等)。ssrn_id3728842_code667 ssrn_id3728842_code667 ssrn_id3728842_code667

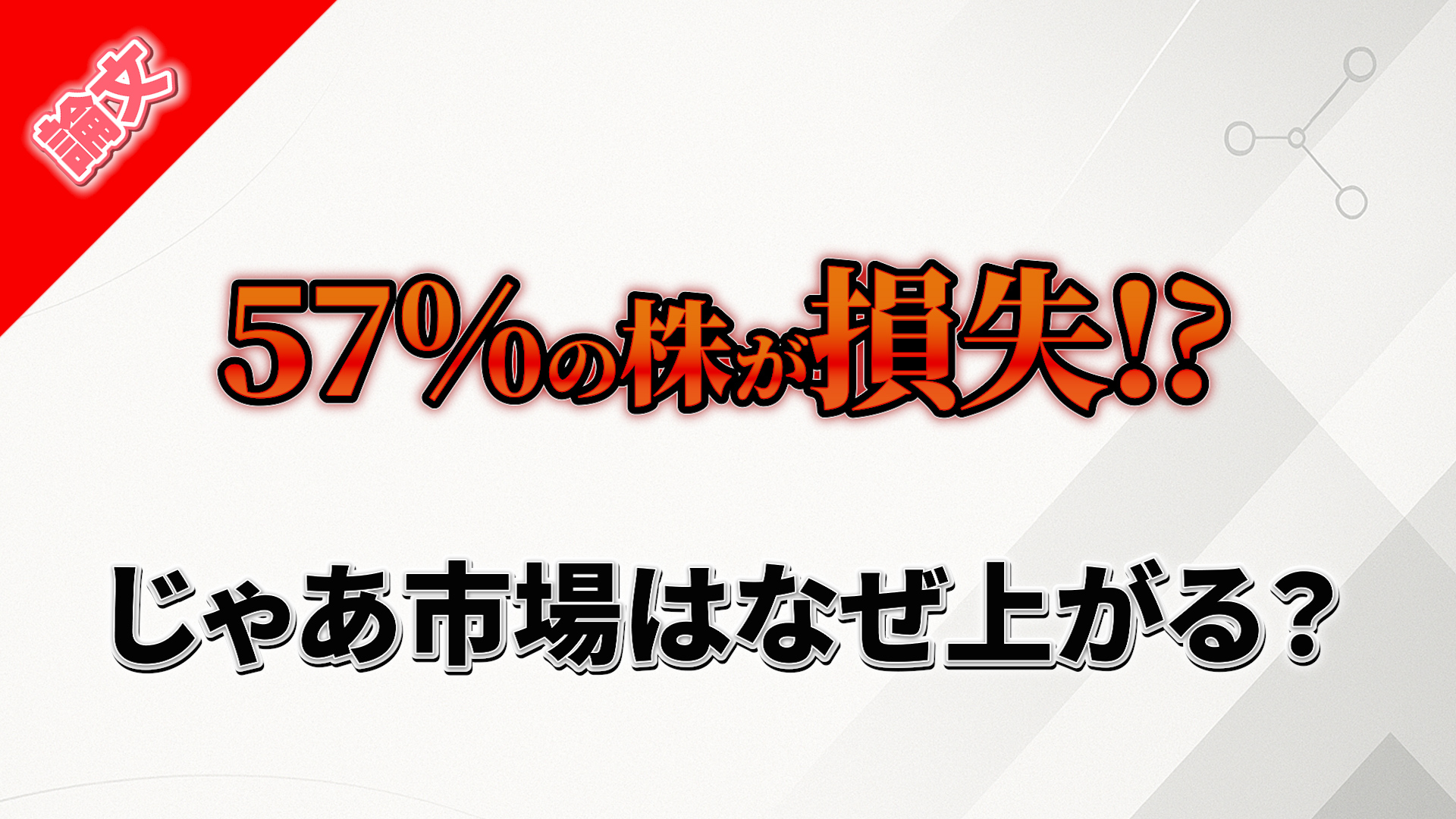
コメント
コメント一覧 (3件)
Elexbettv is great for catching live games. The stream quality is top-notch. Watch here: elexbettv
Looking to get in on the Lotus365 action? The lotus 365 download process is super smooth. Got it running on my phone in minutes. Def recommend giving it a go. Grab your lotus 365 download today!
Hello pals!
I came across a 153 awesome website that I think you should visit.
This platform is packed with a lot of useful information that you might find interesting.
It has everything you could possibly need, so be sure to give it a visit!
[url=https://chandigarhofficial.com/what-are-the-top-online-casino-games-to-easily-win/]https://chandigarhofficial.com/what-are-the-top-online-casino-games-to-easily-win/[/url]
Additionally remember not to overlook, everyone, which one at all times may within this particular publication locate solutions to the most confusing queries. The authors attempted — lay out all of the information via an most understandable manner.